Column 15

ゴルフには柔軟性が不可欠?ゴルファーに多いケガ・痛みの原因とは?ストレッチ方法を解説
- スポーツ
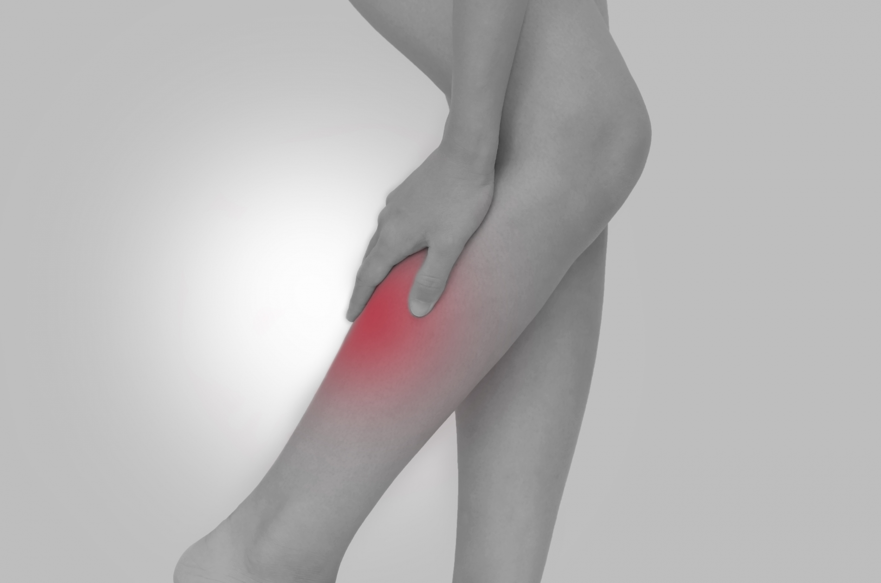
スポーツなどで激しく、あるいは急に体を動かした場合に起こる怪我の1つに肉離れ(筋挫傷)があります。主に太ももやふくらはぎなどの筋肉が裂けたり破れたりすることで発生し、患部を動かせないほどの激痛とともに内出血が起きるのが特徴です。肉離れが起こった際には、すぐに安静にして、患部を冷やしながら圧迫し、心臓より高い位置で固定することが大切です。
この記事では肉離れの症状や原因、肉離れが起こったときの対処法や肉離れと間違いやすい疾患について解説します。
肉離れとは、筋肉や腱、筋膜が断裂する怪我のことです。肉離れは俗称で、正式には「筋挫傷」と呼ばれます。主に太ももやふくらはぎの部位で引き起こされ、スポーツ中や急な動作の後に発生するケースが多いです。
肉離れを発症した際には、「プチッ」という断裂音が聞こえる場合もあり、激しい痛みを伴います。受傷時の激しい痛みのほかにも、損傷部位を押したときの痛みや内出血、皮膚のへこみなども発生するのが症状の特徴です。
肉離れは、スポーツ競技をしている人だけが引き起こす怪我ではありません。重症度もそれぞれ異なるため、自分の症状を確認して、場合によっては医療機関での適切な治療を受けることが大切です。
肉離れは、重症度によって症状や回復までにかかる期間が異なります。それぞれの重症度別に、詳しい症状を解説します。
筋肉の一部が裂けて出血した状態です。腱や筋膜の組織には損傷がなく、自力歩行も可能です。患部の痛みや内出血が確認できます。安静に療養し、無理のないトレーニングを続けることにより、1〜2週間程度で症状が徐々に改善します。
筋肉に加えて、筋膜・腱まで一部損傷した状態です。中等症では、筋肉完全断裂や筋膜・腱が付着する部分の裂離などは見られません。患部の痛みや内出血があり、完全な自力歩行は困難になります。安静な療養と無理のないトレーニングを重ねることで、1〜3か月程度で症状が落ち着きます。
筋肉や筋膜、腱の深い損傷・完全断裂が見られる状態です。筋膜・腱の付着部が裂離するケースも含まれます。強い痛みがあり、自力歩行はほぼ不可能になります。重度の肉離れになると、すぐに医療機関を受診し、適切な処置を受けることが大切です。症状によっては手術を要することもあり、3〜6か月程度の治療期間を要すると考えられます。
肉離れを引き起こすのは、スポーツ選手だけではありません。スポーツをしていない人でも、いくつかの要因から肉離れを引き起こす可能性があります。
肉離れの原因と、それぞれの原因から肉離れを予防するための方法について解説します。
肉離れの原因の1つとして、筋肉疲労の蓄積が挙げられます。
激しい運動や筋力トレーニングを行う日が続くと、筋肉疲労が少しずつ蓄積します。疲労が蓄積すると筋肉が凝り固まり、肉離れを引き起こす要因となるため危険です。
筋肉疲労の蓄積による肉離れを防ぐには、運動後の疲労回復を心がけることが大切です。運動後に、ストレッチなどクールダウンをしっかり行いましょう。足に痛みや熱などを感じた場合は、アイシングをするのも1つの方法です。
栄養バランスのよい食事と適切な休養も、筋肉疲労の回復に役立つため積極的に取り入れましょう。
ウォーミングアップ不足は、肉離れを引き起こす大きな要因です。
ウォーミングアップをしっかり行えば、筋肉や腱の柔軟性が高まり、関節の可動域も広がります。反対に、ウォーミングアップが足りていないと、筋肉や腱が硬いまま運動することになり、肉離れにつながる危険な状態となります。
太もも・ふくらはぎのストレッチを行うことで、肉離れの発症を予防します。特に、久しぶりに運動する人は身体が凝り固まっているので、入念な準備運動を心がけましょう。
体内の水分不足も、肉離れを引き起こす要因です。
体内の水分が不足すると、筋肉の柔軟性が低下し、肉離れを引き起こす可能性が高い状態になります。
特に、運動中は汗をかいて水分不足になりやすいため、こまめな水分補給が欠かせません。運動前後もあわせて、しっかりと水分を補給しましょう。
肉離れが起こったときの対処法として、「RICE処置」が役立ちます。「RICE処置」とは、「Rest(安静)」「Icing(冷却)」「Compression(圧迫)」「Elevation(拳上)」の4つの頭文字を合わせた、基本的な応急処置の対応手順です。
| Rest(安静) | 患部を固定し、安静な状態に保つ |
|---|---|
| Icing(冷却) | 患部を水や氷などで冷やす |
| Compression(圧迫) | 患部を包帯やサポーターなどで圧迫する |
| Elevation(拳上) | 患部を心臓より高い位置に上げる |
肉離れを起こすと、筋肉の損傷に伴い、皮下出血が見られることもあります。激しい痛みと体内の出血を抑えるために、「RICE処置」の中でも「Rest(安静)」と「Icing(冷却)」が大切です。
肉離れのような痛みを感じたら、すぐに運動を中止して安静にします。痛みの少ない姿勢を見つけて、テーピングやタオル、板などで固定するとよいでしょう。患部に氷をあてて冷やすと血管が収縮するため、出血を少なく抑えるのに効果的です。
その上で、患部を包帯やサポーターで圧迫し、枕やクッションを使って心臓より高い位置に上げることで内出血を減らせます。
肉離れには「RICE処置」が役立つものの、あくまでも一時的な応急処置です。症状の具合によって、応急処置の後は速やかに医療機関を受診し、適切な処置を受けるのが望ましいです。痛みが少ない場合でも、専門的な治療プログラムを受ければ、早期回復を見込める可能性が高まります。
医療機関では、肉離れの治療法として物理療法が行われることもあります。物理療法とは、超音波や微弱電流などのエネルギーを使用して施術する方法です。痛みを和らげたり、細胞の修復を促したりと、施術によってさまざまな働きがあります。
肉離れと似た症状を持つ疾患として、こむら返りと筋膜炎が挙げられます。足の痛みを肉離れだと決めつけると、間違ったケアを行う恐れがあり危険です。
こむら返りと筋膜炎がどのような疾患なのかを知り、肉離れとの違いについて理解を深めましょう。
こむら返りとは、主にふくらはぎの筋肉に起こる痙攣のことです。「足がつる」とも呼ばれ、ふくらはぎのほかに足の指や足裏、太ももなどに起こる場合もあります。
こむら返りは、筋肉の異常な収縮によって引き起こされ、激しい痛みを感じるのが特徴です。脱水や身体の冷え、運動不足などが要因となり、就寝中や急に身体を動かした際に起こります。
こむら返りも肉離れも激しい痛みを伴うため、運動中にこむら返りになると、肉離れと勘違いする可能性が高まります。筋肉の損傷や断裂を伴う肉離れと比べて、こむら返りの激しい痛みは通常数分程度で収まる点が違いです。
筋膜炎とは、筋肉の周りを覆う筋膜が炎症を起こすことです。水分不足で筋膜が硬くなると柔軟性を失い、筋肉の伸び縮みがうまくいかなくなります。筋肉をしっかり動かせずに、筋膜が癒着して炎症を起こして強い痛みを生じるのが、筋膜炎の特徴です。
筋肉を覆う筋膜は全身にありますが、主に足裏や腰、背中などで発症することが多い傾向です。筋膜炎の原因として、強すぎる運動負荷や慣れない運動、急な身体の動きなどが挙げられます。特に、マラソンなど足裏への衝撃が強い競技スポーツは、足底筋膜炎(足底腱膜炎)を引き起こしやすくなります。
毎日負荷の強い運動を続けていると、肉離れと筋膜炎のどちらも引き起こす可能性があります。足の筋膜炎を発症すると、激しい痛みから肉離れと間違える人も少なくありません。肉離れと筋膜炎は、MRI検査によって診断が可能です。
肉離れとは筋肉や腱、筋膜が断裂し、強い痛みや内出血といった症状が起きる怪我のことです。主に太ももやふくらはぎで発生しやすく、軽症の場合は自力歩行も可能でありおよそ1~2週間で治りますが、重症の場合は手術を要するケースもあります。肉離れは、筋肉疲労の蓄積やウォーミングアップ不足、水分不足などで筋肉が硬いまま急な動きをすると起こりやすく、スポーツをする方以外にも起きうる怪我です。
もし、肉離れが起こってしまった場合は、医療機関を受診し適切な治療を受けましょう。また、電気刺激療法や超音波療法などの物理療法を効果的に活用し早期回復を図りましょう。

監修者プロフィール
福井 直樹 先生
理学療法士
学校法人響和会 和歌山リハビリテーション専門職大学 教員
(一社)日本物理療法学会 理事
(一社)日本理学療法学会連合日本物理療法研究会 評議員