Column 14
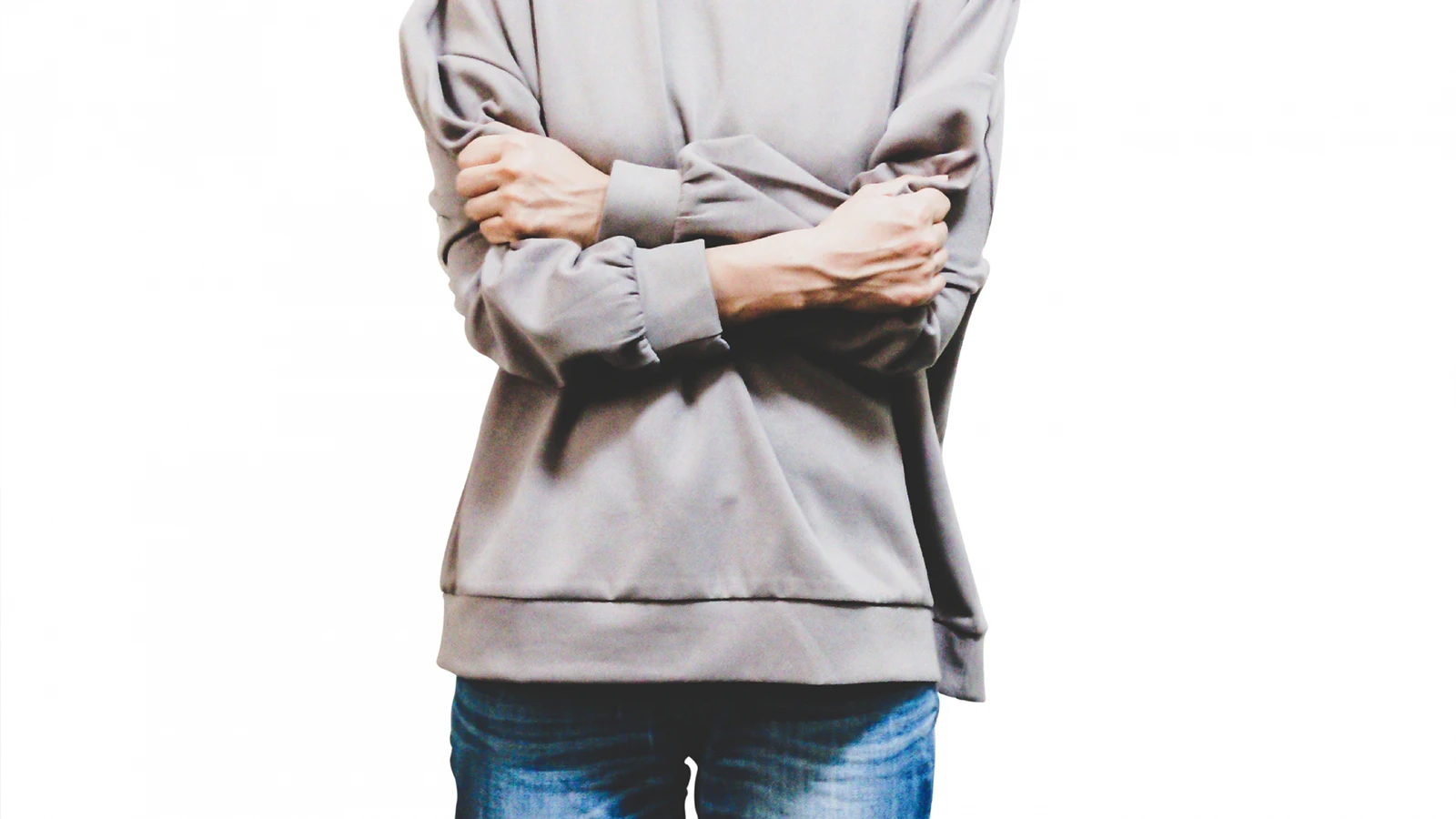
冷え性改善の方法は?冷え性の症状や原因を合わせて解説
- 健康のお悩み

更年期障害とは、一般的に45歳から55歳にかけての「更年期」と呼ばれる時期に女性が経験する、身体や精神の不調のことです。更年期に女性は閉経するため、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が減少した結果、さまざまな症状が現れます。代表的な症状には、のぼせ・ほてり・冷え、肩こり・腰痛、めまい・頭痛、疲労感、気分の落ち込みや不眠・集中力低下、消化器官の不調などがあります。症状には個人差がありますが、重症の場合は治療が必要となることがあります。
この記事では、更年期障害の原因や代表的な症状、対策方法について解説します。
更年期障害とは、女性の更年期と呼ばれる時期に見られる、日常生活に支障をきたすほど重い症状が出現することです。
そもそも更年期とは、月経が完全に停止する「閉経」の前後5年、合計10年間の時期を指します。一般的な閉経年齢は50歳前後であり、おおむね45歳~55歳が更年期と呼ばれる時期です。
更年期になると体内のホルモンバランスが崩れて、身体にさまざまな症状が現れます。更年期になった方の身体に現れるさまざまな症状は「更年期症状」と呼ばれ、中でも重い症状が「更年期障害」です。
なお、更年期障害がどのように発現するかは個人差があり、症状が比較的軽い方や自覚症状がない方もいれば、日常生活を送るのが大変になるほど重い症状が現れる方もいます。
更年期障害が発現する主な原因としては、「エストロゲン」の分泌量が低下することが挙げられます。
エストロゲンは卵胞ホルモンとも呼ばれ、卵巣から分泌される女性ホルモンの一種です。エストロゲンの分泌は脳によってコントロールされていて、若いうちは十分な量のエストロゲンが分泌されます。
しかし、閉経に近い更年期になると、脳が指令を出しても卵巣がエストロゲンを十分に分泌できなくなります。結果、脳と卵巣の連携が乱れて、心身の不調や自律神経の乱れといった症状が出るという仕組みです。
ただし、更年期障害の症状が発現しても、症状がずっと続くわけではありません。エストロゲンの分泌低下による体調の変化にも身体は慣れて、年月を重ねれば症状は徐々に軽減すると考えられています。
更年期の身体にはさまざまな症状が現れ、特に重症度が高い場合は治療が必要になります。
自分が更年期障害かどうか気になる方は、下記のチェックリストを使って症状を確認しましょう。
「頻繁にある」が多い方は重症度が高い可能性があるため、医師に相談することをおすすめします。
(出典:ヘルスケアラボ「更年期障害チェック」)
(出典:東京都産業労働局「40代、50代は更年期を心配するお年頃・・・・・・困っている症状で、受診が必要かどうかセルフチェック!」)
以下では、更年期障害によく見られる代表的な症状を6つ紹介します。
のぼせ・ほてりは、「ホットフラッシュ」とも呼ばれる更年期障害の代表的な症状です。
のぼせは頭に血が上ったように熱くなり、ほてりは頭だけでなく身体にも熱感が生じます。どちらも熱感がある部位に発汗を伴うことが特徴です。汗が止まることなく出続けて、衣類が濡れるほどの異常発汗を起こすケースもあります。
逆に、更年期障害の冷えは手や足の先を中心として、身体に冷えを感じる症状です。冷えは更年期ではない女性にも多い症状であり、更年期障害ではより症状が重くなる傾向があります。
更年期になると血流が低下して、肩こりや腰痛を感じやすくなります。エストロゲンの分泌量が減少することによる自律神経の乱れや、加齢による筋肉・骨の衰えなども、肩こり・腰痛の症状を強める要因です。
また、同じ姿勢で作業をし続けていたり、精神的な緊張を感じていたりすると、肩こりや腰痛につながります。肩こり・腰痛をなるべく防ぐためには、長時間作業をする際に同じ姿勢を続けることは避けて、ストレッチなどで筋肉をゆるめることが大切です。
更年期には脳の血管壁の痙攣や収縮が起こりやすくなり、めまい・頭痛をおぼえます。
更年期障害のめまいは、急に立ったときや体勢を変えたときに発生して、目の前が暗くなってフラフラとする感覚になることが特徴です。一過性の症状であることが多く、しばらく安静にしていればめまいは鎮まります。
更年期障害の頭痛は「頭全体が痛い」「後頭部の付近が痛い」「ひどい肩こりを伴う」など、症状の出方が人によってさまざまです。
更年期障害の疲労感は、身体のホルモンバランスが崩れることによって発生します。「何もする気がしないほど疲れを感じる」「激しく動いていないのに身体にだるさを感じる」などが更年期障害特有の疲労感です。
また、更年期の時期は子どもの独立や親の介護など、ライフステージが大きく変化しやすい時期です。生活環境の変化によって心身にストレスがかかりやすいことも、疲労感の原因と考えられます。
「すぐ気持ちがふさいでしまう」「ベッドで横になっても寝付けない」「仕事に集中できない」といった気分の落ち込みや不眠・集中力低下は、更年期障害特有の症状です。
気分の落ち込みや不眠は生活リズムの乱れにつながり、体調不良を起こしやすくなる悪循環が発生します。
ちょっとしたことでイライラと気が立ったり、不安感をおぼえたりすることも、更年期障害特有の精神症状と言えます。これは、精神を落ち着かせる作用がある「セロトニン」というホルモンが、更年期になると減少することが原因であると言われています。
更年期障害の症状として、胃や腸などの消化器官に不調が現れることもあります。消化器官の動きは自律神経がコントロールしていて、更年期になって自律神経が乱れると消化機能も正常に働かなくなるためです。
結果として胃や腸のぜん動運動がうまくできなくなり、消化不良による下痢や便秘、胃腸の痛みなどが現れます。
また、食事を取ったときに吐き気を感じたり、食欲が減退したりする症状が出る可能性もあります。食欲低下による栄養不足にも注意が必要です。
更年期障害は、軽症であれば生活習慣の改善によって症状が軽くなるケースが多いとされています。
更年期障害の対策方法を3つ紹介します。
更年期障害の対策としては、イソフラボン・カルシウム・タンパク質・ビタミンなどの栄養素をバランスよく摂ることが大切です。特に豆類に含まれるイソフラボンはエストロゲンによく似た働きをするため、更年期障害の症状緩和に役立ちます。
定期的な運動は脳の活性化や心肺機能を強化する効果があり、更年期障害の予防・軽減にもつながる対策方法です。
ウォーキング・ジョギングといった有酸素運動や、ヨガやストレッチなどの身体に負担をかけすぎない軽度の運動は、毎日無理なく継続できます。
ストレスが溜まると心身が緊張し、更年期障害の症状が悪化しやすくなります。入浴・マッサージ・アロマセラピーなど、自分に合う方法でストレス発散を図ってみてください。
更年期障害に悩んでいる方は、まずは生活習慣の改善による対策がおすすめです。
重い更年期障害に悩んでいる場合、婦人科のある病院・クリニックなどで治療を受けることを検討してください。
婦人科のある病院・クリニックでは以下のような治療を受けられます。
更年期障害の症状に対して効果が期待できる漢方薬を処方します。更年期障害対策として代表的な漢方薬は当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)・加味逍遙散(かみしょうようさん)・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)などです。
ホルモン補充療法は、卵巣機能の衰えによって減少したエストロゲンを外部から補充する治療法です。エストロゲンの補充はエストロゲン製剤によって行います。エストロゲン製剤には飲み薬・貼り薬・塗り薬などいくつかの種類があり、医師と相談して自分が使いやすい形態の薬を使用します。
更年期障害の症状には生活環境などの社会的因子、加齢による身体的変化などさまざまな要因が絡んでいます。カウンセリングや心理療法による診療では、自身の悩みや不安を医師に話して、症状に向き合って生活するためのサポートや健康管理のアドバイスを得られます。
更年期は、女性のライフステージにおいて避けられない現象です。しかし、生活習慣の改善によって、更年期に伴うさまざまな症状を軽くすることが期待できます。食事の栄養バランスを見直し、エストロゲンに似た働きをするイソフラボンを多く含む大豆などの食べ物を取り入れることがおすすめです。また、運動習慣を身につけたり、リラックスできる時間を作ってストレスを発散したりするのも大切です。
ただし、更年期障害の症状は人によって異なり、重症化するケースもあります。更年期障害の症状が重く、日常生活を送るのも大変な場合は、婦人科のある病院やクリニックを受診し、治療を受けてください。

監修者プロフィール
福井 直樹 先生
理学療法士
学校法人響和会 和歌山リハビリテーション専門職大学 教員
(一社)日本物理療法学会 理事
(一社)日本理学療法学会連合日本物理療法研究会 評議員